|
設計者の視点/DIY

BT-houseは未完成の家・育てる家がテーマです。
工務店には生活できる最低限の工事を依頼して、多くの仕上げや収納製作は住みながらのDIYで行いました。
必要になった時に必要なものを付け足していくように考えているので、入居して半年たった現在でもまだまだ完成とはいえない状態で、ここに本棚をつくろうか、あそこは漆喰をぬろうか、など日々考えています。5年後には、壁を追加して、部屋を増やしているかもしれません。未完成だからこそ変化できる可能性をたくさん持っていて、これからも家造りを楽しんでいけるのです。
そんなプロジェクトであったため、工事は解体と設備工事が大部分を占め、またDIYも多く取り入れているので、付け加えてデザインするというわかりやすい設計の部分はほとんどありませんでした。
このプロジェクトは私の自宅のリノベーションであるため、設計者と住まい手の線引きがあいまいなところはあるのですが、そんな中でも設計者の役割は重要であったと感じています。

この壁は壊せるのか、天井を剥がすとどうなるのか、などの基本的な判断はもちろん、中古らしさを引き出すため、既存のソースを生かしてスケルトンの天井としたことや接着材の跡が残った土間床を生かしたことは、解体で削りだす設計でした。
また、DIYを取り入れる上では、工務店に依頼する部分とDIYで行う部分を明確にしておく必要があります。DIYは楽しむことが大事です。考え方を誤るとストレスにしかなりません。どこまでのDIYを、どのようなスケジュールで行うかなどをしっかりと検討しておく必要があるのです。

もともと自分たちで好き勝手にカスタマイズできることを望んでいたので、DIYを取り入れたことは自然の流れだったのですが、自分の家や材料のことを学ぶことができるDIYはとても大切なことだと思っています。住まい手自身で建物に手をいれて更新することが出来れば、10年後は今よりも良い家になっていると思うからです。
今回のような解体とDIYが多くを占めるプロジェクトにおいても、家をデザインしながら、プロジェクトを総合的にコントロールできる設計者の役割が重要であることを強く感じました。(森川)
●関連リンク
|
BT-HOUSEの完成までのプロセスはこちら ⇒ |
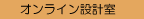 |
|
BT-HOUSEの完成写真はこちら ⇒ |
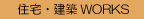 |
(PREV)←
→(NEXT)
|